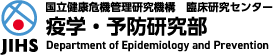第139回検討会概要《デジタル技術を用いた精神科患者支援の潜在性》
前の記事 | 次の記事開催概要
日 時:2025年9月6日(土)14:00-17:00
場 所:エッサム神田ホール2号館
特別講演:デジタル技術を用いた精神科患者支援の潜在性
講 師:熊崎 博一 先生(長崎大学)
抄 録:最近のデジタル技術は目覚ましい進歩を遂げている。デジタル診療はアクセシビリティの向上、継続的なサポート、コスト削減と効率性の向上に寄与する。デジタルフェノタイピング(Digital Phenotyping)はデジタルデバイスを通じて個人の行動、健康状態、生活習慣などのデータを収集し、分析する技術である。機械学習と合わせることで精神疾患の評価、診断およびスクリーニングへの応用が期待される。AIベースのチャットボットは、非対面で初期段階の支援やトリアージに役立つ潜在性がある。製薬会社はデジタル治療アプリケーションの開発にしのぎを削っている。大規模言語モデルには診断精度の向上、パーソナライズされたケアへの期待がかかる。またデジタル技術を用いた支援研究は、現在までの精神科医療の現状と課題を再確認する機会になる。
演者は現在まで精神科患者を対象としたAI、ロボット技術、仮想現実をはじめとしたデジタル技術を用いた支援の研究を展開してきた。本講演では、現在まで世界各地で展開されているデジタル技術を用いた精神科患者支援について概説する。その上で、演者らが行ってきたデジタル技術を用い精神科患者支援研究についても紹介し、デジタル医療を用いた精神科診療の今後の展望について説明する。
総合討論:Digital Phenotyping活用の障壁と可能性
ファシリテーター:大崎 陽平 先生(ヘルスデザイン株式会社)
概 要:総合討議では講演内容に関する質疑応答と事前アンケート調査結果の概要を説明した。ロボットによるアイコンタクトの重要性に関連し、人とのコミュニケーションにおいても同様の意義があることへの確認や、同じく診察時の同席ロボットの話題に関連してWebミーティングでも同様の効果を得ることができるのか、など研究結果から導き出された内容に即してその応用に関しての質疑応答、ディスカッションが行われた。また各国の診断差異の現状や診断基準の問題、AIを使用した検診の効率性と課題なども話し合われた。事前アンケート結果では、精神科医療または産業保健上でのDigital Phenotyping活用を想定した場合の懸念や障壁、精神科医療全般の課題、メンタルヘルス対策におけるデータ活用への期待と懸念などの意見を紹介した。